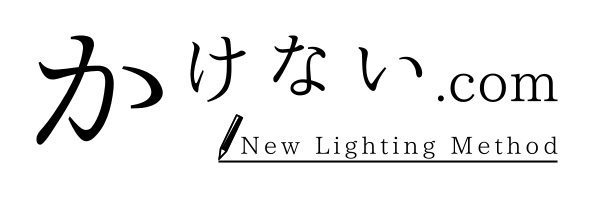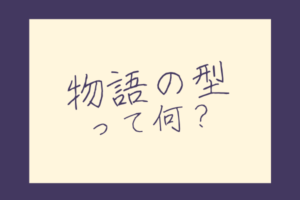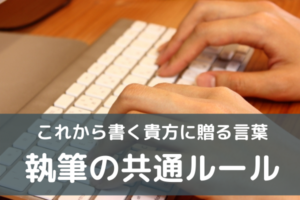梗概って、どう書けばいいの?
小説の公募に必須な梗概(こうがい)。どう書いていいか、迷っていませんか?
実は物語の型を使うと、公募用のあらすじが楽に書けます。
本記事では、梗概の書き方をご紹介しますね。
本記事の内容は、最後まで物語を説明する時に有効です。文庫本の裏や商品説明文、作品紹介のあらすじにはそぐわないので、用途にご注意ください。
梗概を書く前に
まず梗概を書くルールを整理しておきましょう。
大抵は、梗概に次のようなルールが定められています。
- 物語を最後まで書くこと
- 文字数(800字以内)
公募によって、求められる内容は異なります。書く前に、必ずルールを確認しておきましょう。
梗概の役割について、あらすじと梗概、要約の違いとは|類語とニュアンスを解説に記載しています。あわせて参考にしてください。
物語の型はどんな話か
物語の型とは、「面白くなる物語の公式」です。
詳細は別記事で詳しくご紹介しますので、しばしお待ちください。
複数ある物語の型ですが、基本となる話は同じです。そこで物語の型のベースとなる話を、ギュッと要約してテンプレートにしました。
このテンプレートに当てはめることで、楽に梗概が作れます。
見本:物語の型のテンプレート
『とあるところ』にいる『どんな』『主人公』は、ある日『冒険』しなければいけなくなる。『行くか』迷った末に、主人公は『旅立つ』決意をする。
『小さな勝利』と『敗北』を繰り返しながら、ゴールへと近づく主人公。ようやく『勝った!』と思ったけど、それは『見せかけのゴール』だった。
一気にどん底へ落ちる主人公。『苦悩』するが、『打開策』を見つける。そして『最終決戦』へと挑み、『決着』がつく。その時主人公は、『何か』を手にしている。
物語の型の使い方
『』に具体的な内容を入れると、それだけでざっくりとした梗概が作れます。
試しに、桃太郎の梗概を作ってみましょう。
例題:昔話「桃太郎」の梗概
桃から生まれたという不思議な出自を持つ桃太郎は、自分を拾い育ててくれたおじいさんとおばあさんと幸せに暮らしていた。しかしある日、突如村が鬼に襲われる。悲しむおじいさん・おばあさんの顔を見て、桃太郎は鬼退治に行くことを決意をする。
犬・猿・雉と仲間を増やしながら、鬼ヶ島へ向かう桃太郎。鬼たちの猛攻撃に遭い、激戦を繰り広げる。
しかし犬・猿・雉の猛勇のおかげで、辛くも勝利する桃太郎。鬼から謝罪を受け、二度と襲わないことを約束させる。こうして桃太郎は宝物を手に、村へと帰るのであった。
言い訳
多くの人が知る「桃太郎」にしましたが、短いストーリーなので要所が少なかったですね。例として適切ではなかったことをお詫び申し上げます。
さて、かなり創作して補ったのですが、いかがでしょうか? 普段の桃太郎と、印象が変わるのではないでしょうか?
このテンプレートは、あくまで「流れ」です。細かい部分は変更して構いません。ただし流れは壊さないよう、注意しましょう。
梗概作りのコツ
梗概には、次の三点を明記しましょう。
- どんな誰が
- どうして
- どうなった
読み手は、どんな話か知りません。まずはわかるように記載し、その上で面白くなるよう工夫してくださいね。
物語の型を使って楽に梗概を書こう
本記事のまとめは、次の通りです。
- 梗概作りは、物語の型を使うと良い
- 物語の型は、だいたい同じ内容
- 公募先のルールは守る
素晴らしい梗概が書ければ、それだけで作品への期待度は上がります。
本文の付属品と適当に作らず、ぜひ丁寧に書き上げてくださいね。
推薦図書:SAVE THE CATの法則
物語の流れを知るには、最適な一冊。脚本術ですが、創作全般に生かせますよ。